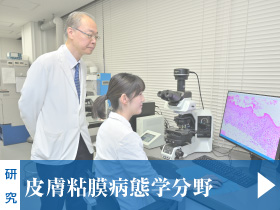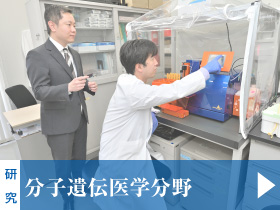| 開催日時 | 令和7年4月15日(火)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 済生学舎1号館 3階 第3講義室 |
| 演 題 | ネクストパンデミックへ向けて~新型コロナから我々が学んだこと~ |
| 講 師 名 | 今村 顕史 (がん・感染症センター都立駒込病院感染症科 部長) |
| 講演内容 |
今村先生はがん・感染症センター都立駒込病院の感染症科部長として、日々の診療を続けながら、病院内だけでなく、東京都や国の感染症対策などにも貢献されておられます。新型コロナウイルスの蔓延時には、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードや東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議の委員として、我が国の保健医療に大きく貢献されました。臨床家として、そして研究者として、パンデミックを乗り越えた経験と、そこから得た教訓をお話しいただきます。 主催分野:救急医学分野 |
| 開催日時 | 令和7年7月10日(木)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 | デジタル脳波解析の基本と応用 |
| 講 師 名 | 久保田 有一 (東京女子医科大学 足立医療センター 脳神経外科 教授) |
| 講演内容 |
高度化するニューロイメージングの時代においても、脳機能の低侵襲、リアルタイム評価に脳波(EEG)が不可欠な診断ツールとして進化を続けている。本講義では、最新のデジタル脳波計による脳波検査の基礎から、高精度な解析技術を解説する。さらに、脳波の臨床応用の未来像を展望する。電気生理学の基礎から最新の応用技術まで、神経科学を見据えた講義を展開する。 主催分野:脳神経外科学分野 |
| 開催日時 | 令和7年5月8日(木)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 | 『大学院で楽しく学び・教えるために!-大学院教育と卒後キャリア形成のヒントー』 |
| 講 師 名 | 小川 令 (日本医科大学 形成再建再生医学 大学院教授) |
| 講演内容 |
大学院教育における教授方法やキャリア形成について大学院生を対象とした講義を行い、人材育成を行っていく。 主催分野:形成再建再生医学分野 |
| 開催日時 | 令和7年12月15日(月)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 | 睡眠の謎に挑む~基礎研究から睡眠ウェルネスへ~ |
| 講 師 名 | 柳沢 正史(筑波大学 高等研究院 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長) |
| 講演内容 |
我々は人生の約1/3を睡眠に費やす。健やかな睡眠は健康と生産性の維持のために必須である。しかし最先端の睡眠学も「なぜ全ての動物が眠るのか?」「そもそも『眠気』の脳内での実態は?」といった根本的かつ身近な疑問に答えることができない。本講演では、これらの謎に挑む私どもの探索的基礎研究に加え、ウェアラブル脳波計測とクラウドAIによる在宅睡眠測定サービスInSomnografによる社会実装研究について紹介する。 主催分野:内分泌代謝・腎臓内科学 |
| 開催日時 | 令和7年9月25日(木)18時00分~19時30分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
①Determinants of Response to Immunotherapy of Cancer ②Cardio-Oncology focused problems and solutions |
| 講 師 名 | ①Edward Gabrielson, ②Kathy Gabrielson(①ジョンズ・ホプキンス大学 病理腫瘍学教室 教授 / ②ジョンズ・ホプキンス大学 病理腫瘍学/分子比較病理学 准教授) |
| 講演内容 |
①Edward Gabrielson先生は、がんの分子病理学およびバイオマーカー研究の第一線で活躍され、肺癌や乳癌などの治療反応性の違いに関する多くの成果を挙げられ、個別化医療の実現に向けて、 腫瘍の分子的特性に基づく診断・治療戦略の構築に貢献されています。本講演では、治療反応性の異なる腫瘍の生物学的背景と治療反応性を予測する臨床検査やバイオマーカーの臨床応用について最新の知見を紹介いただきます。
②Kathy Gabrielson先生は、がん治療薬の心毒性や安全性評価に関する前臨床研究で国際的に高く評価されており、動物モデルを用いた病態解明やトランスレーショナルリサーチに貢献されています。本講演では、心臓腫瘍学(Cardio-Oncology)の概要と心毒性評価を中心とした動物モデル研究についてご講演いただきます。循環器内科医や腫瘍内科医、基礎研究者にとって大変興味深い内容です。 |
| 開催日時 | 令和7年10月3日(金)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟3F 講義室3 |
| 演 題 |
The Eyes are the Windows to the Soul: Use of Automated Infrared Pupillometry to Improve the Care of Patients in Coma |
| 講 師 名 |
Sarah Livesay(Present University of Washington Seattle, Washington Advance Practice Nurse, Neurocritical Care Service) |
| 講演内容 |
集中治療室(ICU)では、正確かつ迅速な神経学的評価が極めて重要であり、瞳孔反応のわずかな変化が生命を脅かす事態の兆候であることもあります。臨床現場での具体的なシナリオを通じて、従来の手動による評価と比較した際の動向測定の利点――神経学的悪化の早期発見の精度向上、医療従事者間での評価の一貫性確保、臨床判断の支援など――を探ります。参加者は、ピューピロメトリーの所見をどのように解釈し、IAP(自動瞳孔測定)をICUの日常業務に組み込むか、またこのツールを活用して患者転帰を最適化する方法について、実践的な理解を深めることができます。 主催分野:救急医学分野 |
| 開催日時 | 令和7年10月22日(水)18時30分~19時30分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
ヴィローム研究の新展開 ~ウイルス学のあるべき姿を探る~ |
| 講 師 名 | 武村 政春(東京理科大学 教養教育研究院 神楽坂キャンパス教養部 教授) |
| 講演内容 |
感染症の主な原因としてのウイルス学研究は、21世紀に入って大きな転換点にある。環境ウイルスと呼ばれる、地球生態系の一員として大きな役割を担っているウイルス研究の進展により、ウイルスの正の側面、すなわち生物の世界とポジティブに相互作用する重要な側面が見えてきた。本講演では、巨大ウイルスをはじめとする環境ウイルスの最新の知見を見据え、将来の医学をささえるための、ウイルス学の真の立ち位置を探りたい。 主催分野:呼吸器・腫瘍内科学分野 |
| 開催日時 | 令和7年10月29日(水)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
遺伝子改変マウスを用いたヒト疾患モデルの作製と病態生理の解析 |
| 講 師 名 | 本田 浩章(東京女子医科大学 実験動物研究所、先端生命医学専攻・疾患モデル研究分野 教授) |
| 講演内容 |
ヒト疾患においては、様々な遺伝子変異が同定されている。しかし、その変異遺伝子が疾患の原因であることを示すためには、目的遺伝子をマウスなどの個体で発現させ、疾患が再現されるかどうかを検証する必要がある。さらに、この様にして作製されたマウスは、疾患モデルとして疾患の分子機構の解明および新規治療法の開発に役立つことが期待される。この講義では、遺伝子改変マウスの概念と作製法、および我々が作製したヒト疾患モデルマウスから得られた知見について紹介し、併せて近年開発され広く個体や細胞の遺伝子改変に応用されているCRISPR/Cas9を用いたゲノム編集について紹介する。 主催分野:皮膚粘膜病態学分野 |
| 開催日時 | 令和7年11月10日(月)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
iPS細胞で挑む“形づくり”と“ものづくり” -病態の解明から細胞製剤まで- |
| 講 師 名 | 神山 淳(早稲田大学 人間科学学術院 教授) |
| 講演内容 |
本講義では、ヒトiPS細胞を活用した「形づくり(神経系の発生や病態の理解)」と「ものづくり(再生医療に向けた細胞製剤の開発)」という2つの側面から、最先端の幹細胞研究を紹介します。 主催分野:呼吸器・腫瘍内科学分野 |
| 開催日時 | 令和7年11月25日(火)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟3F 講義室3 |
| 演 題 |
Academic Surgeonへの憧憬:紆余曲折のち雲外蒼天 |
| 講 師 名 | 根本 慎太郎(大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座胸部外科学 専門教授) |
| 講演内容 |
初期研修医が終了し、これからの医師人生で生業とする専門分野のトレーニングの開始として後期研修が始まる。この頃に上級医から“研究をしなさい”、加えて“大学院へ進学しなさい”と、指導なのか脅迫なのか分からない言葉を投げかけられる。ただでさえ臨床が忙しく、専門医資格取得の単位を稼ぐ必要があり、そして働き方改革だから適当な時間に帰宅しなくてはならない。そんな環境の中で“なんで研究なの”、“大学院なんか無理”、終いに“昔と今は違うんちゃう”と文句も言いたくなる。しかし、歳を重ねて行くと、研究のキャリアの有無が臨床での課題抽出力と解決力に出てくると演者なりに感じている。“研究なんて要らん要らん”と開き直っている輩もいれば、“研究を経験しておくべきだった”と後悔している輩も少なくない。この講演では、 “医師がする研究とは?”、“Academic Surgeonって?”、そして“キャリアのステップアップに研究が役立つの?”の問いについて、臨床医そして研究者の一人の先輩の紆余曲折(徘徊?)のち雲外蒼天という経験を提示しながら答えてみたい。 主催分野:心臓血管外科学分野 |
| 開催日時 | 令和7年11月26日(水)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟3F 講義室3 |
| 演 題 |
米国大学の医学系で日本人が教授になる道筋の一例 |
| 講 師 名 | 山田 和彦(ジョンズ・ホプキンス大学 外科 Director, Xenotransplantation Program) |
| 講演内容 |
山田和彦教授(ジョンズ・ホプキンス大学 外科・教授/ Xenotransplantation Program Director)は、日本医科大学卒業後、米国マサチューセッツ総合病院/ハーバード大学で移植免疫学・異種移植研究を開始。異国の地で挑戦を重ね、コロンビア大学教授を経て、現在は世界の注目を集めるブタ臓器による異種移植の臨床応用計画を率いています。本公演では、米国で教授職に就くまでのリアルな道のりと、最先端医療の現場を体感できる異種移植研究の最前線を語っていただきます。海外で研究・臨床に挑む夢を持つ方にとって、必聴の機会です。 主催分野:形成再建再生医学分野 |
| 開催日時 | 令和7年12月1日(月)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟3F 講義室3 |
| 演 題 |
電子顕微鏡〜基礎から近年の動向まで〜 |
| 講 師 名 | 髙木 孝士(昭和医科大学 電子顕微鏡室 室長・教授) |
| 講演内容 |
電子顕微鏡の歴史は、光学顕微鏡に比べてわずか100年足らずと比較的短いものですが、その間に装置の飛躍的な進化とともに、観察対象に応じた試料作製技術も急速に発展してきました。特に医学・生物学領域における透過電子顕微鏡(Transmission Electron Microscopy:TEM)の試料作製法と観察技術は、1990年代までに一定の完成を見たと言えます。近年では、観察の対象や目的の多様化に伴い、電子顕微鏡の主流がTEMから走査電子顕微鏡(Scanning Electron Microscopy:SEM)へと移行しつつあり、三次元構造の可視化や広範囲の組織像を扱う新技術への関心が高まっています。特にVolume SEMやFIB-SEMによる3次元構造解析、さらには光学顕微鏡との相関観察(CLEM)など、新たな展開が注目されています。一方で、日本の医学教育においては電子顕微鏡の活用機会が減少しており、その重要性や可能性が十分に伝わっていない現状もあります。本講演では、電子顕微鏡観察の基礎から出発し、従来のTEM技術を再確認しつつ、近年の革新的な観察手法や解析技術について、具体的な症例や研究例を交えながらご紹介いたします。電子顕微鏡の“現在地”と“これから”を再考する機会として、研究・教育・診断の現場における電子顕微鏡の可能性を皆様と共有できれば幸いです。 主催分野:統御機構診断病理学分野 |
| 開催日時 | 令和8年2月4日(水)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
生体イメージング研究の最前線~難治性疾患の病態理解と新たな治療を目指して~ |
| 講 師 名 | 菊田 順一(神戸大学大学院医学研究科 未来医学講座 免疫学分野 教授) |
| 講演内容 |
近年、生体イメージングを支える光学技術や光操作技術、AIを活用した生体画像解析技術などの技術革新が著しい。さらに、最新のオミクス解析技術と生体イメージング技術を融合して解析するなど様々な取り組みを行うことで、生体内の複雑な生命現象が次々と解明されつつある。生体イメージング技術は今や、生命科学の分野において幅広く活用され、将来の医療への応用も期待されている。本講演では、これらの生体イメージング技術の革新と、それらを利用した最先端の生命科学研究、臨床応用について議論したい。 主催分野:分子遺伝医学分野 |
| 開催日時 | 令和7年10月20日(月)18時00分~19時00分 |
| 開催場所 | 教育棟2F 講堂 |
| 演 題 |
Advanced Cancer Therapy Drug Related ILD |
| 講 師 名 | Charles A. Powell(Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Professor) |
| 講演内容 |
Charles A. Powell先生は、米国マウント・サイナイ・アイカーン医科大学において、呼吸器内科学、集中治療医学、睡眠医学を統括する教授であり、世界的に活躍される呼吸器専門医です。肺癌を中心とした呼吸器腫瘍学や薬剤性肺疾患(drug-related ILD)の研究で国際的に高く評価されています。今回のご講演では、「Advanced Cancer Therapy Drug Related ILD」をテーマに、新規がん薬物療法に伴う薬剤性ILDの発症機序、臨床像、診断、治療戦略などについて最新の知見をご紹介いただきます。 主催分野:呼吸器・腫瘍内科学分野 |
※過去の特別講義Aはこちら
2024年度はこちら。